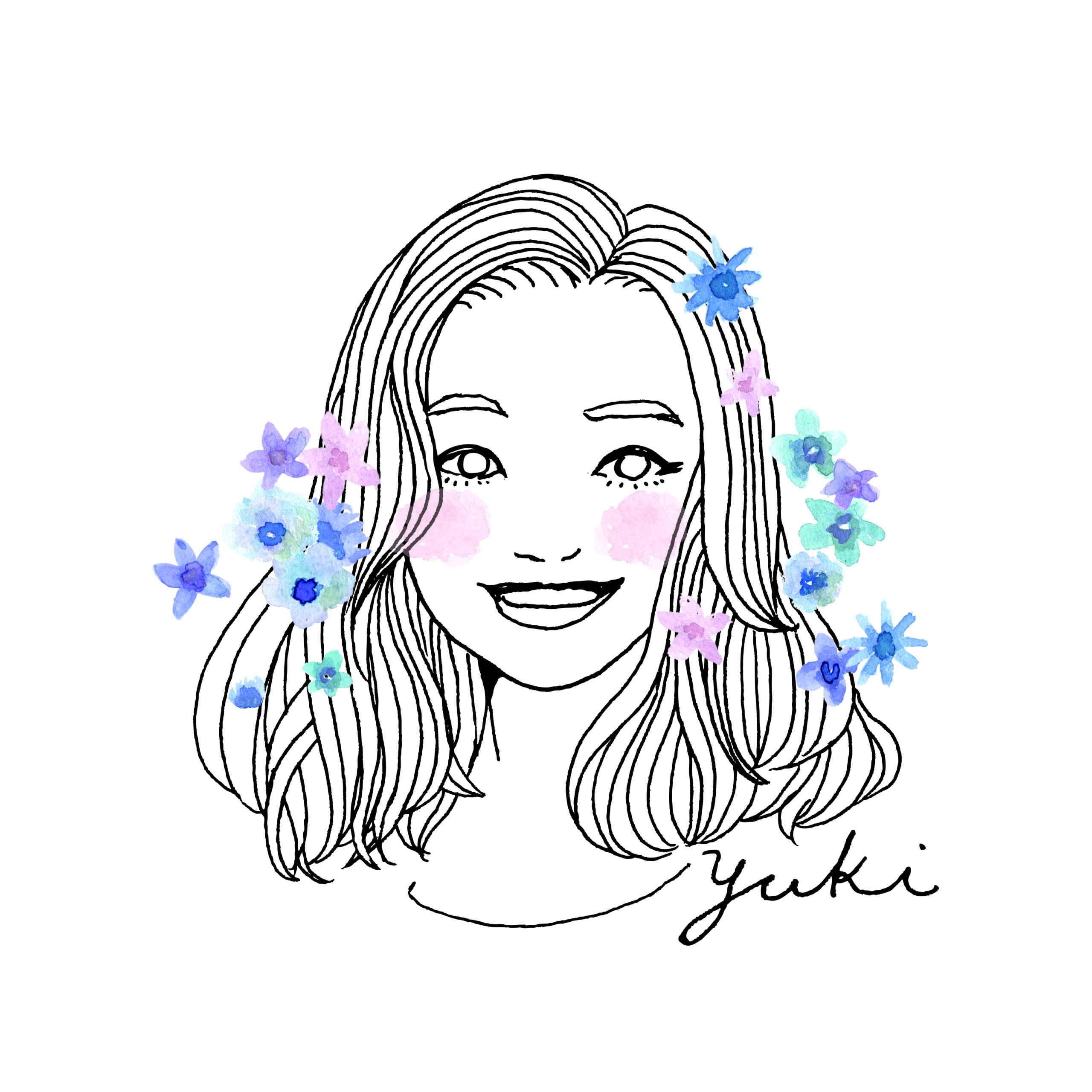目次
−【Yuki】初めまして。まず、少しだけご自身の障害についてお伺いさせてください。
−【つっつさん】生まれつき、右腕は肘よりちょっと短くて、左腕は肩からありません。
−現在はDTPデザイナーというお仕事をされていらっしゃるそうですが、主にどういったもののデザインをされているんでしょうか?
−主に印刷物ですね。特例子会社で働いているんですが、そこのデザイン・印刷課にいます。主にパンフレットやキャンペーンチラシの作成など紙媒体全般のデザイン、データ作成を行なっています。
−デザインのスキルは学生時代に学ばれていたんですか?
−そうですね。元々絵を描くことは得意ではなかったんですけど、小学校くらいから好きで。いつか仕事に繋がればいいなと、中学校の卒業文集に、将来の夢はデザイナーと書きました。
−すごい!夢が叶っているんですね!
−だからこそ泣き言は言えないです(汗)正確に言うと子どもの頃は車や家電、家具などの工業デザインがやりたかったんですよね。
−車のデザインとかって花形ですよね。すごく人気もありますし。
−そうなんですよ。でも基本的に足を使っての作業となるので、座ってできる仕事という制約があります。そうすると、どうしても就職先の選択肢が狭くなっていって。で、今から二十数年前、パソコンを触っているとオタクと冷やかされる時代があったんですけど(汗)、その頃に学校の授業でパソコンを使うことがありまして、パソコンで絵を描く楽しさを知りました。そこからこれが仕事になればいいなとパソコンで絵を描く技術を本格的に学び始めました。
−デザインはいつから学ばれていたのですか?
−それもまた環境が良かったのか、家から自転車で通える範囲に、公立でデザイン課がある高校があったんです。そこに通ってデッサンや色彩など基礎知識を学びました。
−学生時代から好きで学ばれてきたことが仕事になっているなんて、本当にすごいですね。
−理想と現実は全然違いますけどね。
−大変なこともあるとは思いますが、羨ましいです。
−そうですね。おかげさまで会社行くのが嫌だなと思ったことはないですね。
仕事で工夫していること、好きなもの作りの技術を活かして

-【Yuki】お仕事される中で自分なりに工夫されていることはありますか?
-【つっつさん】小学校時代に絵を描くときからそうだったんですけど、足で絵を描くから上手いって褒められることが嫌でした。土俵が違う感じがしたんです。上手だねって言われても、その主語には“足で描く割には”というのが付いている気がして。そこをなんとか払拭したいという思いがありました。だから作品だけを見て欲しいというか。
なので、特例子会社で働いていることも、良くも悪くも特例子会社という時点で障害者が働いていると言っているようなものなので、最初は葛藤がありました。だけど考え方を変えると特例子会社は「障害があってもここまでできるんです!」と証明できる土俵に思えたんです。なので工夫というか、お客様の要望にはしっかり答えるようにしています。
−つっつさんは物作りがお好きで、車や自転車もご自身でいじられることが多いとか。
−そうですね。好きなことや興味があることは挑戦しないと気が済まないというか、やれる気がするんです。ドライブレコーダーやETCの取り付け、タイヤ交換くらいは自分一人でできますよ!

-【Yuki】自転車の改造は、どうしたら自分にとって乗りやすくなるか考えて、業者に改造をお願いしたり、ご自身で改造されたりしているんですか?
-【つっつさん】今はそうですね。一番最初に自転車に乗れるようになった時は、父親がどうしたら安全に乗れるかを考え作ってくれたんです。今思うと父親も物作りが好きだったんですよね。
−つっつさんの物作りが好きなのは、お父様の影響を受けていらっしゃるんですね。
子どもが小さい頃に感じたもどかしい気持ち

-【Yuki】つっつさんは現在2人のお子さんがいらっしゃいますが、休日はご家族でどのように過ごされることが多いですか?
-【つっつさん】今はコロナ禍でなかなか外出するのは難しいですが、元々は車を運転することが好きなので、みんなで車に乗って旅行に行ったりしていましたね。日帰り旅行だったり、ちょっと離れた公園行ったりとか。
−お子さんと一緒に公園や外で遊ぶ時など、大変だなと思うことはありますか?
−今はないです。ただ子どもがまだ小さい頃は、外出先で抱っこをせがまる時がありました。私の場合は抱っこ紐などがないと、長時間は厳しいので、どうしても奥さんに負担をかける時がありました。それで奥さんが腰を痛めたことがあって、その時は何とも言えない、もどかしい気持ちでいっぱいでした。やっぱり力仕事は男性の役割であることが多いので、というへんなプライドが邪魔していたのかもしれません。
−でもお子さんが成長して自分でできることが増えると、子どもに何かやってあげることはできないというより、一緒に遊んだりすることで子どもに教えてあげることが増えるという感じですかね。
−いや、今はむしろ逆ですね。上の長女が小学校3年生なんですけど、私が手を借りることの方が全然多くなってきましたね。たとえば、外出中に鞄からスマホ出すという場面でも、今までは自分が座って足で出したりしてたんですけど、今は子どもに出してって言えば出してくれるんです。たまに「え〜!」とか言われますけど(汗)良くも悪くも家族なんです。
−お父さんと娘だとそういうやりとりになることありますよね(笑)でも仲良しなご家族だということが伝わってきます。
−はい。まだまだお父さん子でいてくれるので、今は助かっていますね。
お父さん、どうして腕がないか知ってる?

-【Yuki】お子さんに、ご自身の障害について改めて説明したことはありますか?
-【つっつさん】それ、最近あらためて子どもに聞いてみたんですよ。「お父さん、どうして腕ないか知ってる?」って聞いたら、「鬼に食われたんだもんね」って言ってました(笑)でもちゃんとした理由は知ってますよ。「お母さんのお腹の中にいるときに、何かあって手が育たなかったか、切れちゃったかどっちだよね。」って。
私は「先天性四肢障害児父母の会(以下、父母の会)」に参加してるんですけど、そこで先輩の障害があるお父さんやお母さんたちから聞いた話があって。子どもの保育園の送り迎えとかで、子たちが障害を珍しがって寄ってくるんですよ。その時にどうやって説明するかっていう話で。そしたら、本当のことを真剣に説明すれば、子どもはわかってくれるって言っていて。それで私も、“この手はね、お母さんのお腹に中にいる時に〜”ってちゃんと説明してたんです。おそらく娘はそれを聞いて覚えたのかもしれないですね。なので改まって子どもに説明した覚えはないですね。
あと、何度説明してもしつこく聞いてくる保育園の子どもたちに「お父さんやお母さんの言うこと全然聞かないでいたら鬼に腕を食べられたんだ」って話した時に、横から娘が、「違うでしょ!生まれた時からなかったんでしょ!」とか言って。
−娘さんから説明してくれたということですか?
−そうなんです。で、他の子が来て、「え、手ないの?」って話しかけてきた時にも、娘が「そうだよ、私のお父さん手がないんだよ!」って、勝手に私の袖をめくり上げて説明してくれて。拍子抜けというか、娘に助けられました。
−うちは、日頃から色々なことに対してあまり重く捉えないようにしていて。障害のこともオープンですし。それが逆に悪い面もあるんですけどね。私の知り合いに車いすの人がたくさんいるのですが、そう言う人たちのことよく知っている分、街中で車いすの人を見かけたら、娘が「あの人も車いすだー」とか言って指差したり。それって普通はあまり言わないじゃないですか。だけど、自分も知ってるんだよっていうことをアピールしたいのか、そういうところがあって。必ずしも全ての人が障害に対してオープンなわけではないですし、言われて嫌な人もいますしね。だけど自分は障害を隠す性格でもないから、オープンにして暮らしているので、子ども達も周りの障害がある人に対して壁を持たずに接するのかもしれません。
-つっつさんは父母の会で予め子育てに関する情報を得ていたようですが、今はそういった集まりに参加する若い方は多くないのかなと思っていて。学校生活が楽しくなったり、仕事で忙しくなる年齢でもあるからだと思うんですが。
-若い方の会員はやっぱり少ないですね。その父母の会は40年以上の歴史がある会で、多い時は全国で1000家族くらいが参加する大きな会だったんです。だけど今は当時の7割くらいに減ってきてるみたいです。けれど会員が減ることが悪いことではなくて、もっと言うと、こういった会がなくても、私たちが不自由なく生活できる世の中を目指しているのです。会員の減少の要因の一つに、ネット環境が発達してきたことがあげあられると思います。簡単なことだったらSNSとかで情報を得られるので、実際に会うという繋がりを必要としていないんですよね。だから小さい頃に、学校で縄跳びするにも縄を持てないとか、リコーダーを持てないとか、そう言う行事で悩んだ時に会に入って情報を得るんですけども、中高生くらいになると大抵の子がみんな退会してしまうんですよ。けれど私は情報共有だけの繋がりではなく、実際に会って話して、安心する。そんな交流が大事だと思うんですよね。高校生くらいまで残っていれば、日頃のちょっとした話題から、親にも言えない悩みを話してくれる子もいます。
-高校生くらいまで残っていると、その後も会に残る方は多いんですか?
-そうですね。会では希望をすれば中学生くらいから、ボランティアっていう役割になって、自分も障害がありながら、障害がある子ども達と遊んだりするんです。自分が必要とされているとわかると、居場所ができるので会に残ってくれるのだと思います。
-すごくいいですね!お兄さんお姉さんに何でも聞けますし。
–子どもたちは、障害に関する悩みをあんまり直接聞いたりする子は少ない気がしています。けれど直接会って遊んだりして肌で感じるっていうか。周りに仲間がいるんだなと、わかればそれで安心できるのです。
-日頃、周りに障害がある友達がいない状況が多いのと思うので、この仕組みとてもいいですね。そして大人になって自分が親になった時は、今度は子育ての情報交換ができる。こういった集まりの役割は本当に大きいんだなと感じました。
自分ができることを一生懸命やっていれば、自然と役割ができる

-【Yuki】子育てする中で工夫していることは何かありますか?
-【つっっつさん】子育てする中で便利なグッズを使ったり工夫をしていることはなくて。でも、割り切ることは大切かなと思います。できないことはできないので。もう奧さんに頼みます。
-家事や子育てについて、夫婦で分担されていることはありますか?
–家の中の分担だと、例えば掃除は好きなので、お風呂やトイレなどの水回り、掃除機は私の仕事で、料理と洗濯は奥さんというのが暗黙で分担されています。でもそれは障害がどうこうでっていうのは無いですね。基本的には私も1人暮らしをしていたこともあるので、洗濯や、簡単な料理も自分で一人でやっていました。
健常者の人でも家事や子育て、何もしない人もいますからね。それでも家族として成り立つわけで。それも一つの価値観ですよね。
-よく、障害がある女性の中で、旦那さんより家事が上手くできないことに対して少し申し訳ない気持ちになるっていう話がたまに聞くんです。今の時代でも、女の人が家事をやるという意識が根底に残っているのも影響しているんだと思うんですが。
-まぁそれは普通の家族でもありますからね。料理が嫌な人、掃除が苦手な人っていうのを夫婦で補いながらやっていくっていう面では、障害の有無関係なくみんな一緒なのかなって最近は思っています。
-得意な方、できる方がやるということですね。健常者の方でも、奥さんの方が仕事が忙しくて旦那さんが専業主夫になるご家族も増えていますしね。
-自分に期待しすぎてもいけないし、周りの期待を背負いすぎても苦しくなってしまうだけ。でもその分、自分ができることを一生懸命やっていれば、自然と役割ができてくると思うんです。
-私、昔出会った方で、ご自身も生活の介助を受けながらも子育ても楽しまれている方がいまして。その方が“物理的に子どもに何かをしてあげることだけが子育てじゃない。愛情を注ぐということが一番の子育てだ”と仰っていたんです。
– それ、私にとって今すごく腑に落ちるところですね。一生懸命お金を稼いで働いてくるだけじゃなくて、なるべく家に帰って子どもや家族と過ごす時間が多い方が、すごく大事だと思うんですよね。別に何をしてあげるということはないんですけど、ただ一緒の時間を過ごしたり、遊ぶだけで十分だと思うんです。それも、障害があるから一緒に遊べないとかじゃなくて。公園に行って何もしなくても、親はただベンチに座って見守ってるだけでいいんですよね。子どもは「お父さん、お母さん見てて」っていうのが口癖なんですよ。だから本当に見ているだけで一緒に走り回らなくても別にいいんですよね。子どもがしたことを、一緒に共感してくれるっていうことが嬉しいんでしょうね。
父親としてのありたい姿

-【Yuki】子どもが生まれる前に、こんな壁にぶつかったらこんな風に乗り越えようとか、ご夫婦で話し合ったりされたんですか?
-【つっつさん】うちはないですね。本来であれば子どもを産む前に遺伝性なのかとか、そういう話をするのかもしれないですけど。奥さんから聞かれたこともなくて。私が遺伝性じゃないということも知っていたので。だけど100%じゃないですよね、それって。もともと障害がない人同士の子どもに障害がある子が生まれることもありますしね。だから話し合いは一切なかったです。心配はお互いにあったと思いますけど、奥さんがどっちかというと男前の性格なんですよ。だからあんまりそういうことを話さないんですよね。
-つっつさんからは、奥様に将来の子育てについて事前に話したりはしなかった?
-事前にはないですけど、事後で先ほどのように、保育園で娘がいじめられたら嫌だなとかは話しましたけどね。でもそういう話しても奥さんは「え、そんなのないでしょ」みたいな(笑)
-奥さんの器の広さというか、どっしりと構えられてますね!子どもを産む前の夫婦での相談って、ご夫婦どちらかに障害があるカップルの多くは必ずやっていると思っていました。でもそれまでの2人の関係性とか信頼関係などで違ってくるんですね。
-結婚に至ってる夫婦は、話し合っていない方も多い気がします。なんで手がないのか知らずに結婚したとかね。別になんともないから聞かなかったみたいなね、そういう話もよく聞きますよ。それくらいの思いがないと、一緒になろうっていう考えにはならないでしょうしね。
–もし周りに子育てに悩んでいる方がいるとしたら、何かアドバイスはありますか?
– 色々な人に会って、色々なお話をするのがいいかもしれないですね。
-自分と同じ障害とは限らずってことですよね。もちろん障害がある親御さんだけでなく、障害ない親御さんとの会話の中で答えが見つかる可能性だってあるってことですよね。
-そうですね。
-つっつさんにとっての、父親としてありたい姿は?
-自分が尊敬できる人は?と聞かれれば「自分の父親」と答えます。だから父親にしてもらったことは、自分の子どもにしてあげたいですね。父親は今でこそよく話ますが、昔は言葉で話すというより、行動で示してくれる人でした。たとえば、父は手先が器用で物作りも好きな人だったので、何か壊れた時は父親に言えば全部直してもらえたんです。だから私も子ども達が困った時や頼られた時にちゃんと答えられる父親でいたいですね。親は子どもへ与えるものってほとんどないんですよね。だからこそ頼られた時がチャンスだと思っています。いつまでも頼られる存在になりたいですね。
周りに何を言われようと、自分の人生を一番大切に過ごすことが大事

-【Yuki】今後5年後、10年後の理想はありますか?
-【つっつさん】最近は自分に対しての今後は考えていなく、今は子どもが健康でいてくれて、同じ時間をできるだけ長く一緒に過ごしたいというのが一番ですね。本当はほかの誰かのためになることが出来れば理想ですが、まずは家族を優先させたいです(笑)
-子どもを産み育てられるか悩む、障害がある若い人はたくさんいると思うんです。そんな方たちに何か一言お言葉を頂きたいです。
-私達は結婚して2年は夫婦2人の時間を楽しんで、その後、子どもが欲しいと思った時に運良く授かることができたのですが、子どもがいる私にとっては子どもは素晴らしい存在だとしか言えないですよね。けれど、子どもがいなかった時間ももちろん素晴らしい時間だったし、どちらに進んだとしても、周りに何を言われようと、自分の人生を一番大切に過ごすっていうことが大事だと思うんです。どんな選択をしたとしても自分が一番に楽しんでいたら、周りも引っ張るようにその楽しいことに巻き込むことができるので、結局は自分次第なんだと思います。
-子育てや子どもを持つことに悩みすぎず、まずは目の前のことを自分で楽しむということでしょうか。それはもしかしたら障害ある無しに関係なく、子育てしている方全員に当てはまることかもしれないですね。
-そうですね。子どもと一緒にお風呂に入るだけでも楽しいですし。子どもがいなかったら奥さんと2人で外でお茶するだけでも楽しい。
よく、「全然良いことないなぁ」って言いながら、大きな幸せを求めすぎてる人がいますけど、何事も前向きに考え生活していたら、幸せってたくさんあると思うんですよね。
-そうですよね、美味しいコーヒー飲んだとか。
-そうそう!私は夏が好きじゃないですから、10月に入ったあたりのもう夏が終わるっていう感じ(笑)それだけでも今すごい嬉しいですもん。目の前にある、日々の小さな幸せを見つけるってすごく大事で、それを拾い集めていくとすごく大きな幸せになると思うんですよね。まずは自分が目の前にある小さな幸せを見つけて毎日を楽しむ。どんな状況であっても、それが大事だと思います。